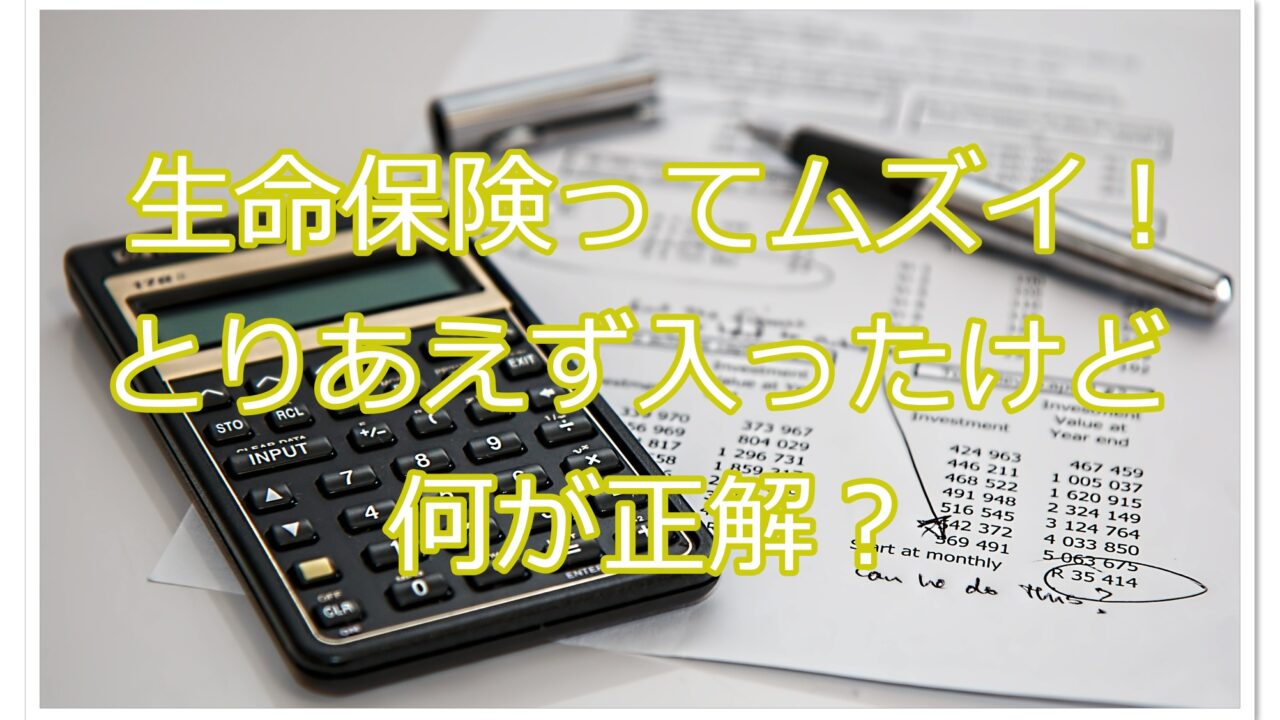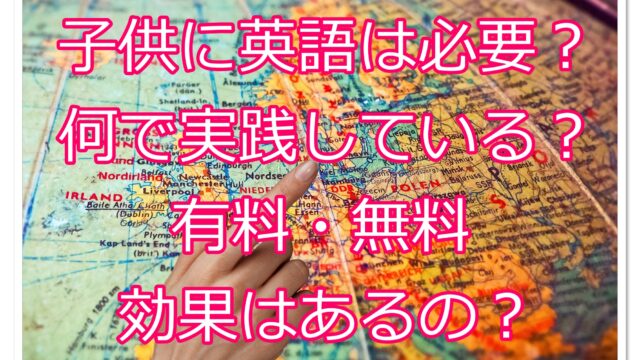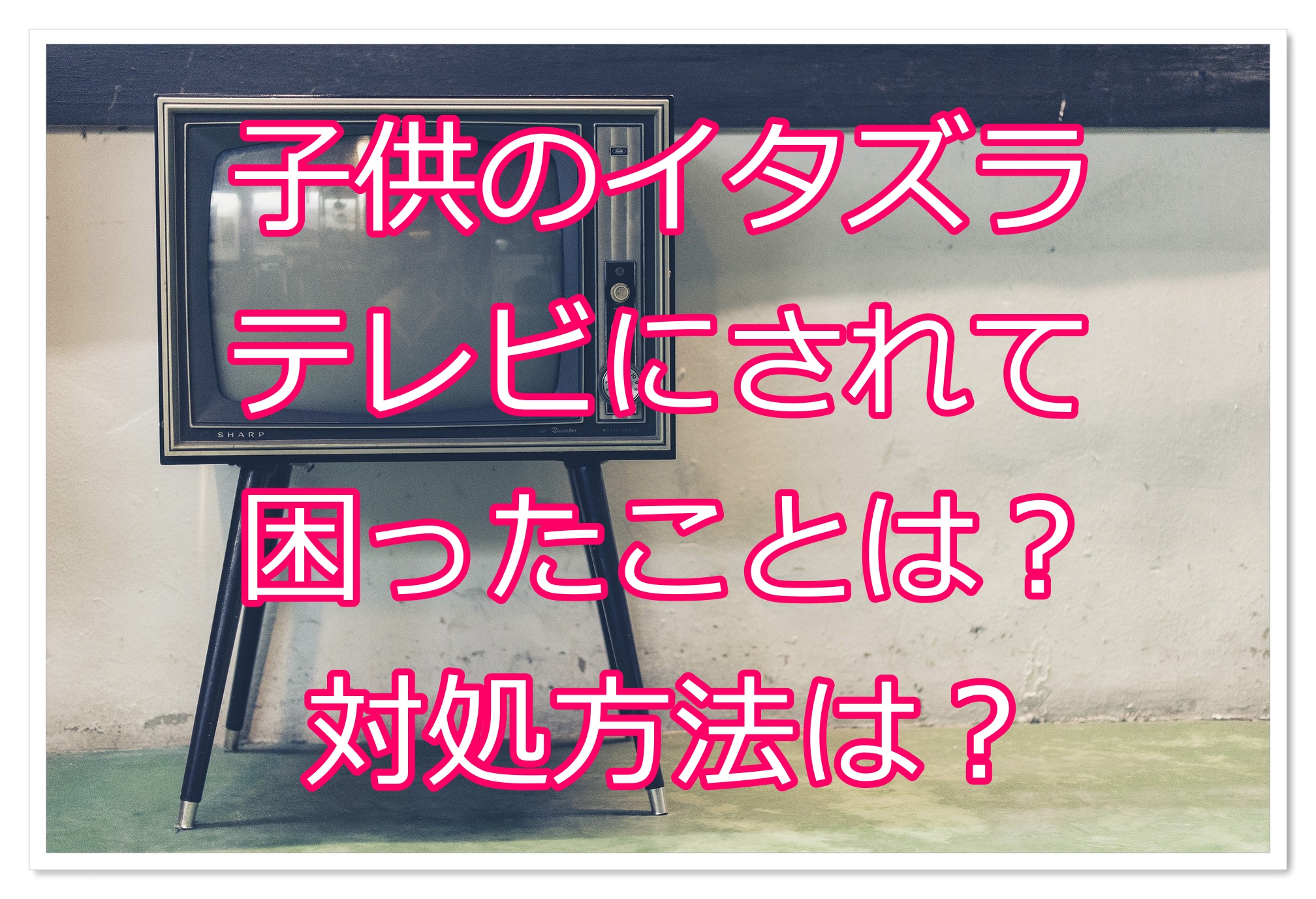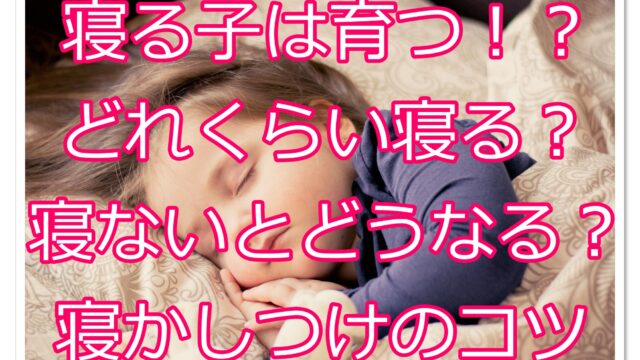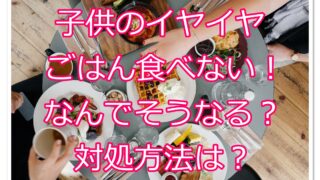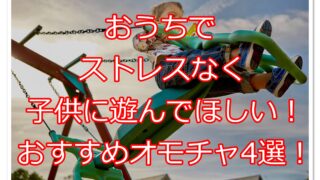ライフステージが変わる瞬間は、人生でそうそう起こるものではないですよね。
就職をしたとき・・・
結婚をしたとき・・・
そして
子供が生まれたときですよね!
子供が生まれたあとって、生命保険をどうするか考えますよね。
というわけで、今回は皆さん迷われる保険についてまとめていきます。
ちなみに私は新卒で日本生命に総合職として入職し、保険商品の販売を行ったり、FPの資格をとったりしたので少しは信頼してもらって大丈夫です(笑)
そもそも保険ってどんな種類がある?
大きく分けて2パターンに分かれます。
1つ目はリスクに備える保険。
2つ目は貯蓄を目的とした保険。
それぞれざっくり解説します。
リスクに備える保険とは?
リスクとは以下の3つです。
死亡に備える保険:死亡時に保険金を受け取れる。
病気やケガに備える保険:病気やケガの治療期間に応じて保険金を受け取れる。
要介護に備える保険:介護が必要になった時に保険金を受け取れる。
貯蓄を目的とした保険とは?
保険会社によって様々な商品があるため一概には言えませんが、一般的な貯蓄目的の商品は以下の3つです。
年金保険:保険料を定期的に積み立て、一定の年齢になった後年金という形で保険金を受け取れる。
学資保険:子供の年齢(18歳前後)に応じて保険料を定期的に積み立て、満期後保険金を受け取れる。満期前に親が死亡した場合は、保険料の払い込みが免除される。
養老保険:満期まで生存していれば満期金が、満期までに生存していなければ満期金と同額の保険金が受け取れる。
パパ・ママの保険はどうしたらいいの?
本題はここですね。
じゃあ保険はどうしたらいいのか?
結論、目的次第なので必ずしもこうすべきということはありません。
・・・これでは答えになりませんね(笑)
では、目的とは何か・・・?
子供が生まれることで保険に入る目的とは?
それは、子供の将来のためですね。
具体的には、子供が独り立ちするまでの資金確保です。
普通に親が生きていれば問題ないのですが、不幸にも亡くなってしまったり、働けなくなった場合、誰が我が子の学費や生活費を捻出するのか?ということですね。
ちなみに、子供の将来という意味では英語もかかせません!
英語についての記事も参考までにご覧ください!
【住】我が子の英語教育どうしてる?費用は高い?そもそも必要? – 新米パパの子育てブログ (ikumen-beginner.website)
具体的に何の保険に入るべき?
死亡保険
まずは死亡保険です。
しかし、どのくらいの保障にしたらいいのかよくわからないですよね?
保険金額は3000万円ほどで十分
保険期間は子供が成人するまでの期間が最低ライン
一つ目の保険金についてですが、なぜ3000万円なのか。
それは、子供一人が高校・大学と進むのに必要なお金が約2000万円~3000万円ほどだからです。
子供が独り立ちするまでの資金確保という目的と照らし合わせると、このような金額設定が妥当だと言えます。
二つ目の保険期間についてですが、なぜ子供が成人するまでなのか。
それは、あくまで子供が独り立ちするまでの資金確保が目的なのに、子供が独り立ちした後(=だいたい成人した後)まで保険をかけておく必要が無いからですね。
学資保険
学資保険は具体的にどういう特徴があるのでしょうか。
ポイントは以下の2つです。
少ないながらも定期預金よりは高い利率で運用できる
契約者(=保険料払い込み者)が死亡した際の保障もついている
学資保険に入る目的は、まずは貯蓄・運用です。
銀行口座にただいれておくよりかは、少しでも増えた方がうれしいですよね。
学資保険の場合、払い込んだ保険料よりも満期後に帰ってくる保険金の方が当然多く、その返礼率は105~110%ほどの商品が多いです。
ただし、条件や商品によってその率は大きく変わってくるので注意は必要ですね。
そして学資保険の最大の特徴は、保障があるという点です。
貯蓄・運用が目的なのであれば、正直学資保険よりももっと効率の良い方法はあります。
でもなぜわざわざ保険という形をとるのか。
たとえば、以下のような学資保険に入っていたとしましょう。
〇払い込み満了は子供が15歳になるまで
〇18歳から22歳まで毎年60万円が受け取れる
〇保険料は毎月1万7千円
何事もなければ、子供が18歳になった年から5年間60万円を受け取れます。
しかし、子供が5歳の時に契約者が亡くなった場合、その後10年間払い込む予定だった保険料の約200万円を払い込まずに、18歳から予定通り5年間60万円を受け取れるのです。
つまり、払い込んだ保険料が100万円だったのに、300万円の保険金を受け取ることになるのです。
保険に入る意味は万が一のことを想定することにあります。
学資保険は、その意味をしっかりと体現していますね。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
ここまで書いた内容は、割と最低限検討すべき保険のラインナップです。
当然人によってケアすべきことが変わってくると思いますので、状況に応じて過不足ないように保険をデザインしてみてください。
しかし、ここまで書いた私の戯言だけでは不安ですよね?(笑)
というわけで、一度保険のプロと相談してみてもいいかと思います!
保険のプロと会話をすることで、自分が備えておくべきことが見えてくるのでオススメです。
是非、自分と可愛い我が子のため、これを機にまじめに保険について考えてみましょう!